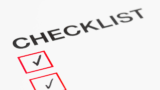このコラムを書いた弁護士:武田 諒

出身:徳島 出身大学:香川大学
離婚および男女間の問題に関しても、依頼者がより豊かな人生を歩むための一助となるべく、精力的に取り組んでいる。 離婚や男女問題は、個人の人生に大きな影響を及ぼす事柄であり、深刻な事態に至るケースも少なくない。こうした状況において、依頼者に寄り添いながら、解決に至るまで伴走することを心掛けている。 また、離婚の場面において大きな影響を受ける立場にある子どもの視点にも配慮し、子どもの観点からも適切な解決を目指している。
財産分与、親権、養育費、慰謝料など、複数の問題が絡む案件を取り扱っており、当事務所に入所以降、多くの経験と実績を有している。
1 モラハラ夫が離婚に応じない理由とは?
(1)モラハラ夫の特徴
モラハラ夫は、経済力や体力といった男性としての優位性を利用して相手を支配しようとする特徴がみられます。
例えば、
①経済的優位性を前提とする暴言
自分の収入を盾に、妻を軽んじる発言を繰り返します。これにより、妻は経済的に自立できないことへの引け目を感じ、弱い立場に置かれるのです。
②家庭内での支配者
自分の意見が常に正しいと思い込み、妻や子どもを長時間にわたって説教したり、人格を否定するような言葉を浴びせたりします。妻や子を劣位的な立場として追い込み支配しようとするのです。
③外出や人間関係の制限
妻の交友関係や行動を監視し、仕事や趣味をすることを阻止するなど、社会的に孤立させようとします。
以上のような特徴が挙げられます。
モラハラ夫のチェックリストについては、こちらを参照ください。
(2) モラハラ夫の心理的背景
モラハラ夫は、多くの場合、社会的に「男らしさ」を強く求められてきた環境で育っています。
そのため、自分の価値を「稼ぎの良さ」「決断力」「強さ」といった点に置きがちです。
・男らしさへのプレッシャー
家族を養うという社会的な役割に対するプレッシャーから、もしそれがうまくいかなかったり、自分より妻の方が能力が高かったりすると、「男としてのプライド」が傷つけられたと感じます。
このプライドを守るために、妻を軽んじたり、支配したりすることで、自分の優位性を確認しようとします。
・依存心の裏返し
一見、強く自立しているように見えますが、実は妻に強く依存しているケースも少なくありません。
自分の居場所が家庭にしかない場合、妻が自立しようとしたり、自分のコントロールから外れたりすることに強い不安を感じ、モラハラで束縛しようとします。
このように劣等感や不安を隠すために、相手をコントロールしようとする心理的背景はモラハラ夫の特徴といえます。
(3) 離婚を拒む理由とそのメカニズム
モラハラ夫が離婚に応じない理由の一つとして、家事的な依存が挙げられます。
表面上は威張っていても、実際は家事や育児を妻に任せきりだったり、精神的に妻に依存しているケースが少なくありません。
離婚すれば、その生活基盤が崩壊してしまうため、離婚を拒否します。
男性としてのプライドも挙げられます。
妻に離婚を切り出されることは、「男としての価値がない」と突きつけられたように感じます。
そのプライドや世間体を守るために、妻を非難し、離婚を拒否することで、自分の優位性を保とうとします。
それがいき過ぎた場合には、相手を苦しめること自体が支配欲を満たす行為となり、意図的に離婚を長引かせるケースも見られます。
このような進捗が困難な状況では、被害者が一人で解決するのは難しく、法律の専門家の介入が有効となります。
離婚となれば、慰謝料・財産分与・養育費・年金分割などの経済的負担が発生します。
特に、不貞行為(不倫・浮気)を行っていた場合、慰謝料の支払い義務が生じる可能性が高く、「お金を払いたくない」という理由で離婚を拒む人も少なくありません。
また、公務員や会社員など、社会的地位のある人は、「離婚した」という事実が周囲に知られることを嫌う傾向があります。
職場や親族に知られるのを恐れ、「離婚に応じること=自分の敗北」と感じてしまうケースもあります。
2 モラハラ妻が離婚に応じない理由とは?
(1)モラハラ妻の特徴
モラハラ妻は、夫の自尊心を傷つけたり、子どもの存在を利用したりするような、より巧妙で精神的な攻撃を仕掛ける傾向があります。
例えば、
①夫の人格や能力を否定する発言
「男のくせに」「稼ぎが少ないんだから文句言わないで」「だからあなたはダメなのよ」といった言葉で、夫の男らしさや能力を否定し、自信を奪おうとします。
②子どもを巻き込む行為
子どもに夫の悪口を吹き込み、家庭内で夫を孤立させようとします。これにより、夫は家庭内に居場所を失い、精神的に追い込まれていきます。
③無視や冷たい態度
夫が話しかけても無視したり、冷淡な態度をとったりすることで、夫の存在そのものを否定し、精神的な苦痛を与えます。
以上のような特徴が挙げられます。
モラハラ妻のチェックリストについては、こちらを参照ください。
(2) モラハラ妻の心理的背景
モラハラ妻は、夫の自尊心を巧妙に傷つけることで、精神的な優位に立とうとします。
その背景には、「愛情の飢餓感」や「強い不安」があることがあります。
・過度な承認欲求
幼少期に親から十分な愛情や肯定的な言葉をもらえなかった場合、大人になってからも、常に夫から「愛されている」という確証を求めます。
しかし、その満たされない気持ちを夫にぶつけ、夫を貶めることで、一時的な安心感を得ようとします。
・見捨てられ不安
夫にいつか見捨てられるかもしれないという強い不安を抱えていることがあります。
そのため、夫の行動を細かく監視したり、誰にも相談させないように孤立させたりすることで、夫を自分の手元に留めようとします。
・自己の無価値感
自分が社会的に認められていないと感じている場合、夫を攻撃してコントロールすることで、自分の存在価値を確認しようとすることがあります。
このように自己肯定感が低く、相手の行動を自分の思い通りにすることで安心感を得る心理的背景はモラハラ妻の特徴といえます。
(3) 離婚を拒む理由とそのメカニズム
モラハラ妻が離婚に応じない理由の一つとして、見捨てられることへの不安が挙げられます。
夫に見捨てられることへの強い不安を抱えている場合、離婚はまさにその恐怖が現実になることだと感じます。
経済的に夫に依存している場合には、なおさら強い恐怖を感じ、夫の収入や財産を失いたくないという思いから、離婚を拒否することがあります。
また、夫を自分の手元に縛り付けておきたいという独占欲から、離婚を拒否し続けるのです。
さらに、加害者意識の欠如が挙げられます。
モラハラをする側は、自分が相手を傷つけているという自覚がほとんどありません。
そのため、「なぜ私が悪者扱いされなければならないのか」「どうして離婚しなければならないのか」と、被害者意識を持って離婚を拒否することがあります。
離婚によって自分の立場が不利になると考え、あえて話し合いを長引かせるケース、被害者をさらに精神的に追い詰めることで離婚を諦めさせようとするケースも見受けられます。
このような進捗が困難な状況では、被害者が一人で解決するのは難しく、法律の専門家の介入が有効となります。
3 離婚に応じないモラハラ夫・妻に対する具体的な対策
(1) 証拠を集める重要性
モラハラ夫やモラハラ妻との離婚を考える場合、まず必要なのは客観的な証拠を集めることです。
モラハラの多くは言葉や態度による精神的暴力であり、証明が難しいのが現実です。
しかし、日記やメール、LINEのやり取り、録音などを記録することで「具体的な事実」として整理できます。
裁判所や弁護士に相談する際に有効な材料となり、相手が離婚に応じない場合でも主張を裏付ける力となります。
もっとも、証拠集めに傾倒するあまり、あなたがさらなるモラハラ被害によって追いつめられては、本末転倒であるため、無理に耐える必要はありません。
離婚に踏み切るのであれば、法律の専門家へ早めに相談することを推奨します。
(2) 別居の選択肢とその効果
次に検討すべきは別居です。
モラハラ環境下に長く身を置くことは、心身への悪影響が大きく、子どもがいる場合にはその生活にも深刻な影響を与えます。
別居は被害者自身または子どもの安全を確保するだけでなく、「夫婦関係の破綻」を示す強い証拠となります。
相手が離婚に応じない場合でも、別居期間を重ねることで離婚訴訟に有利に働く可能性が高まります。
他方、別居したとしてもモラハラ夫・モラハラ妻の対応には気をつけなければなりません。
具体的には、自分から家を出て行ったことを理由として生活費を渡してもらえないケース、子どもとの面会を不当に制限するケースもありえます。
こうした不当な態度には、法律の専門家への依頼や裁判所の調停手続きを利用することを強くお勧めします。
別居のタイミングや別居期間の影響についてはこちらの解説をご参照ください。
(3) 第三者の介入を利用する
第三者の介入を活用することが重要です。
一対一で話し合いを行ったとしても、モラハラ夫・モラハラ妻はあなたの話を簡単に受け入れようとはしないでしょう。
かえって、威圧的な態度で非難されたり人格を否定されたりするなど、さらなる被害に繋がりかねません。
突然出て行ったり、話を聞こうとせず、冷静な話し合いができない状況に陥ることもあります。
無理をせず、信頼できる親族や友人に相談するのはもちろん、弁護士や家庭裁判所の調停制度を利用することで、冷静かつ法的な解決へと進めやすくなります。
専門家が介入することで、モラハラ夫やモラハラ妻の一方的な支配構造を崩し、被害者が適切な権利を守ることが可能になります。
(4) 家庭裁判所での調停を活用
調停では、双方が別室に分かれて話し合いを進めることができるため、精神的な負担が少ないのが特徴です。
調停委員が間に入ることで、相手が話を聞こうとしない場合でも一定の前進が見込めます。
調停の結果、合意が成立すれば、その内容は「調停調書」として裁判の判決と同じ効力を持ちます。
4 モラハラ夫・妻に対して離婚の切り出し方の注意点
モラハラ夫やモラハラ妻に離婚を切り出す際には、感情的な対立を避けることが重要です。
直接的に強い言葉で迫ると、相手はさらに「離婚に応じない」姿勢を強め、状況が悪化しかねません。
できる限り冷静な態度で伝えることが重要となってきますが、離婚に応じてくれない可能性もあるでしょう。
話合いが当事者間で難しい場合には、第三者、法律の専門家の関与や裁判所の調停手続きの利用を検討すべきでしょう。
離婚を切り出す際の予めの検討事項やタイミング等については、以下の記事をご参照ください。
離婚調停手続きに関しては、以下の記事をご参照ください。
5 モラハラ夫・妻との離婚成功事例
(1) モラハラ夫の事例
40代女性は、夫に家計管理を奪われ支出の要否にあれこれ口出しをされたり、子どもが傍にいるにもかかわらず性交渉を強要されたりするなどのモラハラ被害を受けていました。
そして、このようなモラハラ行為を行う夫に対して離婚調停を申立てました。
夫は自らの加害行為を認めず、妻に慰謝料を請求しましたが、約1年数か月の調停を経て、夫からの慰謝料請求は排除した上で最終的に離婚が成立しました。
モラハラ加害者は自身の行為の認識に乏しい傾向があります。そのため、離婚にならざるを得ない状況であっても離婚協議中や離婚調停中でもモラハラ行為を続けてきます。
この事例は、弁護士が介入したことで、夫によるモラハラ行為から依頼者の生活や正当な権利を守ることができたケースです。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
(2) モラハラ妻の事例
40代男性が、携帯電話の登録内容や出張の際のお金の使い方、その他日常生活におけるありとあらゆる点に渡って執着するモラハラ妻に疲弊し、離婚を求めたケースです。
当初、本人で離婚調停を申し立てて対応していましたが、離婚調停は不成立寸前のところになってしまいました。しかし、弁護士介入によって離婚調停での離婚が成立しました。
妻による夫のモラハラ被害は増加してきている状況下で、本事例は、夫側の弁護活動を行い、当事者本人では解決が困難なケースにおいて離婚調停による離婚が成立したケースです。
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
(3) 成功のための戦略
モラハラ夫やモラハラ妻が離婚に応じない場合でも、冷静な準備と法的対応が成功の鍵となります。
有力な証拠を徹底的に集めること(なお傾倒しすぎることには注意が必要です。)
別居を戦略的に活用すること
弁護士など第三者の専門的サポートを受けること
が重要です。
また、相手との直接交渉ではなく調停や裁判を活用することで、感情的な対立を避けつつ前進できます。
6 弁護士への相談と離婚調停の進め方
(1) 弁護士に相談するメリット
弁護士は法律の専門家として、証拠の集め方や調停・裁判での有利な主張方法を具体的に指導してくれます。
専門的な知識や経験から、モラハラ夫・モラハラ妻からの過剰な要求からあなたの権利を守り、離婚に向けて適切に進めることができます。
夫婦間に子どもがいる場合、面会交流や養育費に関する具体的な状況、対処法を提案してもらえます。
長年モラハラに苦しんだ末の熟年離婚では、年金分割や財産分与、生活費の確保が特に重要になります。
「今後の生活が不安」と感じる方は、弁護士に早めに相談し、適切な準備を進めることをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットとして、相手方との直接のやり取りを弁護士に任せることで、精神的な負担を軽減できる点も重要です。
(2) 弁護士選びのポイント
弁護士を選ぶ際には、離婚や男女問題に特化していて実績が豊富で、依頼者の悩みに寄り添って対応してくれるかが大切です。
相談しやすさ、説明のわかりやすさも重要な判断基準です。
また、HPや口コミ、お客様の声からモラハラ事案の解決事例がある場合には、経験があるといえます。
弁護士との相性や実績の有無で判断するのが良いでしょう。
岡山香川架け橋法律事務所は、離婚・男女問題に強みを持った弁護士法人です。
豊富な事件実績を有し、初めて相談する方にも分かりやすくサポートし、状況に応じた柔軟な支援を行っています。一人で悩まず、まずは気軽にフォームや電話でご相談ください。