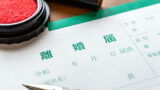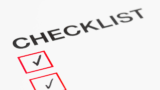出身:徳島 出身大学:香川大学
離婚および男女間の問題に関しても、依頼者がより豊かな人生を歩むための一助となるべく、精力的に取り組んでいる。 離婚や男女問題は、個人の人生に大きな影響を及ぼす事柄であり、深刻な事態に至るケースも少なくない。こうした状況において、依頼者に寄り添いながら、解決に至るまで伴走することを心掛けている。 また、離婚の場面において大きな影響を受ける立場にある子どもの視点にも配慮し、子どもの観点からも適切な解決を目指している。
財産分与、親権、養育費、慰謝料など、複数の問題が絡む案件を取り扱っており、当事務所に入所以降、多くの経験と実績を有している。
このコラムについて
本稿は、妻からのモラルハラスメント(モラハラ)を受け、対応について悩んでいる夫に向けた記事となります。モラハラ妻の特徴や対処法、離婚や法的対応を検討する際の参考となる情報を、弁護士の視点から解説します。
1. モラハラ妻とは?定義と基本知識
⑴ モラハラ妻の定義
「モラハラ妻」とは、婚姻関係にある配偶者に対し、言葉や態度で精神的な圧力を与える妻(女性)を指します。
たとえば、「稼ぎが少ない」「家事ができていない」などと過剰に責め立てる言動はモラハラ妻の特徴の一つです。
夫が妻のこのような言動に反論しても、妻はさらに夫に対して「常識がない」「男のくせに」などと感情的に批判するでしょう。
こうした状況が続けば、夫は我慢を強いられ、家庭生活の中で孤立感や無力感を抱え、共同生活に疲弊していくことになります。
モラハラは昨今、社会問題ともなり、離婚原因としての多くを占めるようになってきています。
男性側が離婚調停を申し立てる際の申立て理由として、「精神的な虐待をする」(注;離婚調停の申し立ての際に離婚原因として選択するチェック項目のひとつであり、この場合には、相手方が自分に対して精神的に虐待をすることを意味します。)を上げる人の人数が増加しています。
例えば、最高裁判所の司法統計によれば、平成16年と令和6年との20年間の違いを比較すると、「精神的な虐待をする」を離婚理由として上げる人の割合が約8%増加していることが分かります。
【平成16年】
夫の申立て総数 19,056件
「精神的に虐待する」を動機とするもの 2,587件(約13.5%)
【令和6年】
夫の申立て総数 15,396件
「精神的に虐待する」を動機とするもの 3,358件(約21.8%)
引用:平成16年度司法統計情報、令和6年司法統計年報(該当ページは48ページ目)
また、夫側がモラハラを行うケースの割合の方が高いものの(令和6年における妻が「精神的に虐待する」を動機として申し立てている割合は約26.2%)、妻からモラハラを受けているケースの割合と大差はありません。
モラハラは男女問わず発生する問題ですが、ここでは「モラハラ妻」に焦点を当て、モラハラ妻の特徴・対処法を解説します。
⑵ モラハラの法的側面
①離婚原因になる可能性
モラハラは、配偶者に対する精神的な暴力行為ですから、離婚原因となる可能性があるのです。民法では「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚が認められますが、モラハラはこの「重大な事由」に該当する可能性があります。
ただし、モラハラには立証(証拠が存在するか)の問題があることと、モラハラのDVとは異なる特徴である「程度問題」という点にも注意が必要です。
すなわち、身体に対する直接の暴力であるDVは、一度でもこれがなされれば、程度の問題を問わず、それだけで離婚原因となります。
例えば、夫が妻を押し倒す、髪を掴む、頬を叩く、頭をどつくなどという暴力行為は、これらの結果、たとえ妻がケガをしなかったとしても完全に暴力行為であることは明らかです。当然、刑法上の暴行罪(刑法208条)に問われ得る行為なのです。
それゆえ、これらの行為はたった一度であっても夫婦間の信頼関係は地に落ち、それ以後は婚姻を継続し難いものとして離婚原因に該当します(民法770条1項5号)。
他方でモラハラの場合には、モラハラ行為が、配偶者に対しての暴言(「アホ」「ボケ」「こんなこともできないの」など)や、束縛(日に何度もメールないしLINEや電話での居場所確認をする、お金の使い道に事細かに口出しをしたり、報告を求めたりするなど)、長時間の説教をするなどというものであり、常に「程度問題」が関係してきてしまうのです。
すなわち、夫婦の間で多少、口汚く言葉を発することは時折あったとしても仕方ないことなのかどうなのか、その内容や頻度はどの程度だったのか、日にどれくらいの連絡を求めたら「束縛」といえるのか、お金の使い道を問い質すことは単に家計管理の問題に過ぎないのではないかなど、いずれも程度が問題となってしまうのです。
そのほかにも程度問題以前に、そもそも口頭でのやりとりなので「言った」「言わない」の段階で問題となることすらあります。
したがって、モラハラは離婚原因にはなるものの、これを認めてもらうための準備や工夫が重要となるのです。少なくとも自身で判断をし、これはモラハラだから離婚原因になるとか、モラハラを理由とした慰謝料が請求できるはずであるなどと断定をしないようにしてください。
モラハラ行為を理由に離婚を検討している方は以下の記事もご参照ください。
②慰謝料事由になる可能性
モラハラ妻による言葉の嫌がらせは、法律上「不法行為」として慰謝料請求の対象となることがあります。
たとえば、日常的に「役立たず」といった、人格を傷つける発言を繰り返す行為は精神的被害として認定されるケースもあります。
ただし、モラハラは上記のとおり「程度問題」であり、不法行為に基づく慰謝料が認められるかどうか、慰謝料額は事案によって異なってきます。
また、立証の問題からも、証拠関係からモラハラを認めさせられるかについては難しい側面があります。
慰謝料請求に関しても、ご自身で判断することが困難なケースもあります。
そのため、これを認めてもらうための準備や工夫が重要となりますし、モラハラに関する事案に対応できる弁護士に依頼することも良いと思います。自分にとってよい方向性を探るためにも、法律の専門家への相談は非常に有効です。
2. モラハラ妻の特徴と行動パターン
⑴ モラハラ妻の特徴
モラハラ妻の特徴としてまず挙げられるのが、感情の起伏が激しく、機嫌によって相手の行動を左右しようと感情的な言動を行います。
また、自己中心的な思考が強く、自分の感情や意見を常に優先し、相手の考えを聞き入れないあるいは自身の非を認めず謝罪しない傾向も見られます。
さらに、家庭内で夫や子どもを支配しようとする行動が顕著であり、母親としての立場からも圧力をかけがちです。
他にも、モラハラ妻には以下のような典型的な特徴があります。
・暴言や侮辱的な言葉を頻繁に使う
夫を傷つける言葉を平気で言う
・無視や冷たい態度をとる
話しかけても反応しない、素っ気ない態度を取る
・夫の意見を否定し続ける
何を言っても「口答え」「言い訳」として扱う、育児は自分の意向を中心に行う
・夫の交友関係や行動を制限する
外出や連絡先の管理、位置情報の共有を強要する
「実家に帰るのはやめて」「友人とは会うな」など、他者とのつながりを不利に導く
・嘘や誇張した悪口を周囲に言いふらす
夫の評判を下げるような話を親族や友人に広める
・子どもに夫の悪口を吹き込む
子どもを味方につけて夫を孤立させる
・夫の所有物を勝手に捨てる・壊す
趣味の物や大切な品を無断で処分する
・感謝や労いの言葉がない
夫の努力を当然とし、認めない
・外面が良く、周囲には良妻を演じる
家庭内と外で態度がまるで違う第三者の前では好印象を与える
上記の特徴に該当する場合にはモラハラ妻にあたる可能性があります。
弊所でもモラハラに関するチェックリストを用意しているため、活用下さい。
上記の特徴に基づく言動は夫婦関係を悪化させ、夫側が知らず知らずのうちに精神的に追い詰められていくのです。
また、夫が話し合いを試みても、「話にならない」と一方的に遮るケースも少なくありません。
日常生活の中で、あれこれと一方的に責め立てられる状況が続くと、夫側も共同生活に疲弊し共同生活を継続することが困難になってくるため、関係性を冷静に見直すことが求められます。 モラハラ妻の言動は夫の経済的自立や人間関係に大きな影響を与えるため、早期の対応が必要です。被害者は「自分の努力が足りないのでは」と思ってしまいがちですが、明らかに相手が加害者である場合も少なくありません。
⑵ 妻のモラハラが発覚しにくい理由
モラハラ妻の言動は、外からは見えにくく、被害者が男性であることからも周囲に理解されにくい傾向があります。
妻が第三者の前では穏やかで社交的に振る舞っている一方、家庭内でのみ暴言や侮辱、精神的圧力を加えるケースが多いため、夫が被害を訴えても「気のせいでは」「もっと強くなれば」と軽視されがちです。周囲には「優しい妻」を演じ、被害者である夫を誰にも理解されない状態にします。
また、夫自身が「家族の問題は外に出すべきではない」と我慢してしまい、相談の機会を逃すこともあります。
こうした背景により、妻のモラハラは深刻化するまで発覚しづらく、長期的に夫の心身をむしばむリスクがあるのです。
3. モラハラ妻になる原因
⑴ モラハラの原因
モラハラ妻となる原因には、強いストレスが影響していることが多く見られます。
自身が抱える悩みや怒りを整理できず、その感情を身近な配偶者にぶつけてしまうケースが少なくありません。
特に、一人で問題を抱え込む傾向が強い方は、自己防衛のために相手を攻撃するくせがついている場合もあります。
また、プライドが高く、自分の非を認めたくない人は、家庭内で支配的な立場を取ろうとすることがあり、それがモラハラにつながる原因となります。
こうした背景には、育ってきた環境や過去の事情も関係していることもあり、原因は一つではないという点にも注意が必要です。
⑵ 心理的背景と影響
モラハラ妻の背景には、性格や育った環境など心理的な要素が大きく関わっている可能性があります。
特に幼少期に愛情を十分に受けられなかったり、過干渉な親に育てられたりすると、精神的に不安定な傾向が強まりやすくなります。
また、自尊心が低く、自分に自信がない人は、他者を支配したり攻撃的な態度を取ることで心のバランスを保とうとすることもあります。
このような感情のコントロールが苦手なタイプは、無意識のうちに精神的負担を配偶者に押し付けてしまうことが多く、深刻な心身の影響を及ぼすことがあります。
本人に自覚がない場合も多く、対応には十分な注意が必要です。
⑶ モラハラを受けやすい人の特徴
モラハラ妻との関係で悩む男性には、いくつかの共通した傾向があります。
特徴としては、以下の点が挙げられます。
・自己肯定感が低い
自分に自信がなく、傷つけられても、相手の言動を「自分が悪いから」と受け止めてしまう
・争いを避ける傾向が強い
衝突を恐れて我慢し続けるため、相手の支配がエスカレートしやすい
・優しすぎる、気配りが過剰
相手の機嫌を常に気にしてしまい、自分の意見を言えなくなる
・過去に支配的な親との関係があった
幼少期に親からの過干渉や否定を受けて育った場合、支配されることに慣れてしまっている
・孤独や見捨てられることへの恐怖が強い
関係が壊れることを恐れて、理不尽な扱いにも耐えてしまう
・経済的・精神的に依存している
相手に生活や精神面で頼っていると、立場が弱くなりやすい
・感情を表現するのが苦手
怒りや悲しみをうまく伝えられず、第三者に相談できずに内にため込んでしまう
こうした特徴の人は、相手の理不尽な要求や暴言に対しても我慢してしまいがちで、結果としてモラハラが長期化・深刻化するリスクが高まります。
また、子どもや家庭を守ろうとする気持ちが強いあまり、耐えることを選んでしまうケースも多く見られます。
モラハラ行為は、自身及び子どもにとっても悪影響であり、長期化・深刻化した場合には、抜け出す気力がないほど疲弊していたり、モラハラ行為から心身を守れなくなっていたりするケースも多くあります。
モラハラ妻との関係性を見つめ直したいと考えているのであれば、早期の相談が重要となります。
4. モラハラ妻への対処法
モラハラ妻との離婚を考える中で、知っておきたい対処法がいくつかあります。
⑴第三者の同席のもとでの話合い
モラハラ妻との1対1の話し合いで夫婦関係の改善を求めたとしても、モラハラ妻は夫側に責任があるとしてまともに話し合いに応じない可能性も高いでしょう。
また、無理やり話をしようとしてもトラブルになる可能性もあると思います。
そのため、1対1での話し合いではなく、中立的に話を聞いてくれる第三者に話し合いに入ってもらうことが一つの方法です。
モラハラ行為の原因など互いの関係性を見直し、中立的な第三者の意見も踏まえて、今後の関係改善を試みましょう。
中立的第三者の意見であれば、モラハラ妻も受け入れる可能性もあり、関係改善が実現できる可能性もあります。
ただし、モラハラ妻の特徴として、家庭外の第三者に対しては話を受け入れるような態度を取り、話し合い後に夫に対して責め立てたり、話し合いで了承した内容を守らなかったりする可能性もあります。
⑵ 別居
妻との関係改善が望めない場合には、共同生活を続けてもさらに心身が疲弊し問題も深刻化するため、離婚を決意する方もいるでしょう。
別居は、離婚に向けた第一歩となり、妻のモラハラ行為から自身を守る意味でも、有効な手段となります。
妻のモラハラ行為によって、これ以上夫が傷つく必要はなく、関係改善が困難であれば離婚に向けて別居をする優先度は高いと言えます。
他方、別居をする場合であっても夫婦間で生活保持義務を負っているため、収入状況や子供との生活状況に照らした婚姻費用(配偶者がもう一方の配偶者に対して支払う生活費等)の支払いが問題となる場面もあります。
モラハラ妻との離婚問題を円滑に進めるためには、モラハラにおける事案を扱う弁護に相談することが有益だと思います。
⑶ 離婚協議・調停
夫が離婚を切り出しても、モラハラ妻は感情的な言動や批判的な言動を繰り返し、離婚に応じないことも考えられます。
また、離婚には応じるけれども、親権、財産分与、養育費、面会交流、慰謝料などの離婚条件について過剰な要求や制限を行ってくる可能性もあります。
この場合には弁護士を立てて、離婚協議を進める選択もあります。
モラハラ事案での経験を有する弁護士であれば、交渉対応の進め方や慰謝料請求の可否についても助言をもらうことができます。
また、離婚協議で折り合いがつかない場合は、離婚調停を申し立てることも検討しなければなりません。
離婚調停手続きに関しては以下の記事をご参照下さい。
離婚調停においても、離婚協議と同様に互いに離婚意思および離婚条件が合致する場合には離婚が成立します。
離婚調停において初回期日で双方の意見が合致することはほとんどなく、中立的立場の調停委員(双方の言い分を交互に聴取し、すり合わせを行う委員)が双方の対立点を整理し、当事者が歩み寄れるかを検討しながら合致点を模索していきます。
あくまで調停委員は中立的な立場であるため、一方に有利になる目的で話し合いを進めたり、助言したりすることはありません。
弁護士に相談、依頼することで、経験や知識に基づきモラハラ妻からの過剰な要求に屈することなく、夫自身の権利利益を保持した解決を実現できるよう進めることができます。
さらに、弁護士に依頼する場合には、直接弁護士が相手方と対応するため、あなた自身が直接相手方から更なるモラハラ行為や過剰要求を受けて精神的な負担を被ることを避けることも出来ます。
状況に応じて適切な対処を講じるには、法的知識が必要です。早い段階で弁護士に相談し、法的なリスクの指摘と整理を行い、正しい対応を検討することをおすすめします。
⑷ 証拠を残すこと
モラハラ行為による離婚原因、慰謝料請求の主張には、立証の問題があることは前述のとおりです。
モラハラ妻からのモラハラ行為(モラハラの声やLINE、メールのやり取り等)をメモや録音で記録することで、上記の主張の証拠として用いることができます。日時や内容、感じたことを詳細に残し、裁判等で利用できるように備えましょう。
他方、証拠を集めることに気を取られ、モラハラ行為を受け続け被害が拡大することは避けなければなりません。
⑸ カウンセリングを受ける
モラハラ妻からの支配を受けている状況、精神が疲弊している状況だと、自身が被害者であるとの冷静な判断はできないですし、モラハラ妻との離婚協議・調停においても争う程の力が残っていない場合もあります。
夫婦の関係性を改善したい、あるいは、離婚をしたいなど冷静な判断ができなければ、今後もモラハラ行為を受け続け深刻化することになります。
そのため、専門家のカウンセリングを受けることで、元の状態まで心を回復させる必要もあります。
誰にも相談できずに孤立すると、被害は深刻化します。カウンセラー以外でも、信頼できる家族や医師、弁護士等の第三者に状況を伝えることで、現状を客観視するきっかけになります。
5. 離婚事例
6. まとめ
モラハラ妻の言動に疲弊している場合には、関係性を見つめ直すこと、具体的な対処法を行うことで自身を守ることが、まず大事になってきます。
他方、モラハラ行為の存在を理由に離婚および慰謝料請求が認められるかの判断は容易ではありません。
離婚や慰謝料請求を検討している場合には、モラハラ事案での解決経験を有する弁護士に相談、依頼をすることで法律的観点からのアドバイスを受け、適切なサポートによってモラハラ妻からの過剰要求やモラハラ行為を避け、交渉を進めることが可能です。
弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所では、モラハラ事案の離婚事件や慰謝料請求事件の実績を有する弁護士が所属しており、対応を行います。
当事務所では、モラハラ・DV・浮気・不倫や不貞行為・離婚等に関するご相談を幅広く取り扱っております。対応エリアは岡山・香川を中心に、遠方の方にはオンライン相談もご案内可能です。
離婚・モラハラに関するコラムや一覧ページを当事務所のサイトに掲載しておりますので、サイトマップをご活用ください。
ご相談を希望される方は予約の上、相談を実施する流れとなっております。
モラハラ妻との生活に疲れを感じ、離婚や法的手続きを考えている方は、まず自分を責めないことが大切です。精神的な被害は見えにくいですが、確実に心をむしばんでいきます。
ひとりで悩まず、早めに専門家へ相談することで、将来に向けた一歩を踏み出すことができます。
当事務所では、多数の離婚案件を通じて、相談者にとって得になる法的選択を提案しています。
あなたの声に耳を傾け、法的手続きの道筋を与え、安心を提供するのが私たちの仕事です。まずは気軽にご相談ください。あなたの期待に応えるべく、全力でサポートいたします。